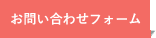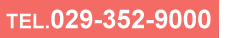ブログ
4.192025
WEBコーダーとして喰っていくには
アクセスログを見ていると、2022年4月17日に公開したこちらの記事が、今もなおよく読まれているようです。
https://www.web-realize.com/2022/04/17/webcoder/
公開から3年が経過した現在、状況は大きく変わりました。AI技術の進化、特にChatGPTの登場によって、WEB制作の世界も大きな影響を受けています。しかしながら、当時も今も、私たちリアライズがWEB制作者に求める「本質的な資質」は基本的に変わっていません。
現在も、「WEB制作者として働きたい」といったご相談や応募をいただくことが多々あります。リアライズでは、学歴や性別ではなく、実力を重視して採用を行っています。ただ、正直に言えば、私たちが求めるレベルに達している方は決して多くはありません。
多くの応募者が、自身のポートフォリオサイト(例:Foriioなど)に制作したバナー画像やデザインを並べ、「こういった制作ができます」とアピールされます。ところが、実際に公開・稼働しているWEBサイトとなると、途端に情報が薄くなります。あったとしても、いわゆるスクール課題でよくある歯科医院のデモサイトなど、見慣れたテンプレートをアレンジもせずそのまま提出されるケースが非常に多いのです。
こうした作品を何度も見ている私たちからすると、申し訳ありませんが、その時点で採用対象から外れてしまいます。
不思議なのは、「なぜ自分自身の力でオリジナルのサイトを作ってみようとしないのか?」という点です。
本気でWEBコーダーとして食べていこうと決めたのであれば、時間が許す限り手を動かし、模擬サイトでもいい、自分の力で1から設計・構築したサイトを数多く作って、腕を磨くべきです。
そのうえで、自分で考えて制作したサイトを実績として提示し、「これが自分のスキルです」と言えるようにする。さらにいえば、知人・友人に声をかけて、無料や格安で構わないから店舗や企業のホームページを作らさせてもらい、”実際に稼働しているサイト”を増やす。私がもし未経験者の立場だったら、間違いなくそうやって実績を積み上げていきます。
たとえば、バナーデザインが苦手であっても、コーディングのスキルに優れていれば、リアライズとしては積極的に採用を検討します。なぜなら、コーディングに長けていれば柔軟に仕事を依頼することが出来るからです。
WEB制作の現場というのは、常にイレギュラーの連続です。
予定になかった機能の追加、バナーエリアの構成変更、あるいは納期直前の仕様変更、そんなことは日常茶飯事です。最初に作成したワイヤーフレームや仕様書通りに進む案件など、ほとんど存在しません。サイトが完成するにつれ、クライアントから機能の追加や修正を求められるのは当たり前の出来事です。
ですから、「きれいに整ったデモサイト」だけを見せられても、本当にその人が柔軟に対応できるのか、現場のプレッシャーに耐えられるのかが、見えてこないのです。
では実際のところ、コーダーとして“喰っていけている”人はどのくらいいるのでしょうか。
独学で必要な技術を身につけるのは、かなりハードルが高いのが現実です。そのため、多くの方がWEBデザインスクールに通ったり、オンラインセミナーで基礎を学んだりしていると思います。現在は学習環境も豊富に整っており、YouTubeやSNSでも情報は簡単に手に入ります。
しかし、そこから実際に飛躍して「仕事として成立させている人」がどれほどいるかというと――私たちの体感では、おそらく10人に1人。いや、もしかするとそれ以下かもしれません。
これは決して夢を潰したいわけではありません。ただ、現場を見てきた人間としての率直な感想です。
理由は明確です。「技術を覚えること」と「仕事として成り立たせること」は、まったく別物だからです。
HTMLやCSSの基本構文を覚えただけでは、当然ながら制作の仕事にはなりません。仕事として求められるのは、「限られた条件のなかで、求められたものを、正しく・早く・柔軟に仕上げる」力です。
加えて、制作現場では「これは仕様にないけど対応できますか?」「納期が1日早まりました」「画像の比率が全然違うものが届きました」といった“想定外”が次々と起こります。それに対して一つひとつ冷静に対処できるか、そこがプロとしての分かれ道になります。
コーディング技術を学んだからといって、すぐに「仕事になる」と思ってしまうのは非常に危険です。そして、学んだ技術を“いかに現場で活かすか”を考え、行動できる人だけが、生き残っていける世界なのです。
リアライズが見る “本当に強いコーダー” の特徴
では、私たちリアライズが「この人は本当に強い」と感じるコーダーとは、どういった人物なのか。
決して“完璧な人”という意味ではありません。むしろ、いかに現場での課題を乗り越える力を持っているか、そこが評価の分かれ目です。以下に、私たちが重視しているポイントをいくつか挙げてみます。
1. 調べて、自力で答えを導ける人
WEB制作において「わからないこと」が出てこない日はありません。エラー、仕様変更、ブラウザによる挙動の違い、プラグイン同士の競合など、日常茶飯事です。
そんな時、“とにかく聞く”のではなく、“まず調べてみる”姿勢があるかどうかは非常に重要です。
Google検索や公式ドキュメント、GitHub、Stack Overflowなど、プロなら当然使いこなしてほしい情報源です。「調べてもダメだったので質問します」という姿勢であれば、むしろ歓迎されます。
2. 仕様変更やトラブルに動じない“現場対応力”
ホームページ制作は理屈どおりにいかない場面の連続です。納期直前に構成が変わる、急に動画を入れてほしいと言われる、あるいは第三者が書いたコードのバグを修正しないといけない――そんな“想定外”にどれだけ対応できるか。
**コーディングスキル以上に、「気持ちが折れない力」**が強さの本質だったりします。
3. 見えない部分のコードにも気を配る“設計思考”
HTMLやCSSをただ書けるだけではプロとは言えません。
構造が整理されているか、クラス名が適切か、後からメンテナンスしやすい書き方になっているか――そうした「見えない部分の配慮」があるかどうかで、現場の信頼度は大きく変わります。
自分以外の誰かが触ることを想定して書かれているか。
これは現場での評価を大きく左右する要素です。
4. デザインとの“すり合わせ”ができる柔軟さ
最近はFigmaやXDなどのツールをベースに進行する案件が多く、デザイナーと密に連携を取る場面が増えています。
そんな時に「これは無理です」「できません」と言ってしまう人よりも、「この方法ならできますよ」「少しこう変更してもらえれば対応可能です」と提案できる人のほうが、はるかに重宝されます。
技術だけでなく、**“伝え方”や“柔軟な発想”**が強さになるということです。
5. “わかりません”が言える勇気
意外に思われるかもしれませんが、「自分の限界を正しく伝えられる人」こそが、現場で信頼されます。
知ったかぶりや、その場しのぎの回答は後で必ず問題になります。むしろ「そこはまだ勉強中です」「調べて対応します」と正直に伝える姿勢こそ、長期的に見れば大きな武器になります。
終わりに
「コーディングができること」と「プロのコーダーであること」は、決してイコールではありません。
リアライズでは、完成された美しいデモサイトよりも、イレギュラーに立ち向かう胆力や、現場での応用力、人との連携力を重視します。
WEB業界は、変化が激しく、不確実性の高い世界です。それでもこの業界で“喰っていきたい”と思うなら、自ら考え、動き、乗り越えていく力を磨いてください。
その覚悟がある方と、ぜひ一緒に仕事をしたいと考えています。
このまま記事として完成にしても良い流れですし、末尾に採用ページへの導線や関連記事リンクを設置しても効果的です。必要であれば追加対応しますので、お気軽にどうぞ。